おはようございます。
東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。
相続の手続きを進める中で、困った時はどの法律専門家へ相談しましょう?
法律専門家といえば、弁護士・司法書士・税理士などを思い浮かべる方が多くいらっしゃいますが、行政書士も様々な手続きを業務として行うことができます。
今回は、相続手続きにおいて行政書士に依頼することのメリットやデメリットを解説していきます。
少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。
行政書士が対応可能な相続手続き
行政書士は行政書士法にもとづく国家資格で主に以下の業務を行います。
- 官公署に提出する書類の作成とその代理、相談業務
- 権利義務に関する書類の作成とその代理、相談業務
- 事実証明に関する書類の作成とその代理、相談業務
具体的にどのような業務かイメージしづらいですが、行政書士の業務範囲は非常に幅広く、相続手続きにおいてもさまざまな業務に対応することが可能です。
相続において行政書士が対応できる代表的な業務は以下のとおりです。
相続人の調査、戸籍謄本の取得
相続手続きにおいて、始めにすべきことが相続人の調査です。
亡くなった人(被相続人)や相続人の戸籍謄本を取得して相続人を確定させる作業です。
亡くなった人については、出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要となり、ケースによっては両親や兄弟の出生から死亡までの戸籍謄本も必要になります。
これらを不足なく取得するためには戸籍を読み解く知識が必要です。
相続人が多い場合や相続関係が複雑な場合は、行政書士に依頼することが効果的です。
相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図の申出
戸籍謄本を取得して相続人が確定したあとは相続関係説明図を作成します。
相続関係説明図とは、亡くなった人を中心として、その相続人が誰で何人いるのか、亡くなった人と相続人はどのような続柄なのかを示した図です。
家系図に似ていますが、家の歴史を辿るものではなく、亡くなった人の相続関係を図示するものです。
相続関係説明図と戸籍謄本などを法務局に提出して法定相続情報一覧図の申出を行います。
この申出を行うと、法務局が戸籍謄本をチェックして相続関係が説明図どおりであることを確認し、その説明図に認証文を付けた法定相続情報一覧図の写しを交付してくれます。
この写し1枚で戸籍謄本や住民票の代わりになるため、その後の相続手続きで提出する書類を大きく減らすことができます。
また無料で何通でも交付してもらえますので、複数の相続手続きを同時に進めたいときには非常に便利です。
相続財産の調査、財産目録の作成
相続財産の詳細が不明な場合には、行政書士に相続財産の調査や財産目録の作成を依頼することができます。
具体的には、銀行や証券会社に対する残高証明書や取引明細書の請求、不動産の名寄せや評価証明書の取得、保険会社に対する契約内容の照会などを行います。
これらの調査をもとに亡くなった人の財産目録を作成します。
正確な財産目録があれば、その後の遺産分割協議や名義変更の手続きがスムーズになります。
遺産分割協議書の作成
相続財産について、具体的に誰がどの財産を引き継ぐのかを決める話し合いを遺産分割協議といいます。
分割協議は相続人全員で行う必要があり、1人でも相続人が欠けた状態で行われた場合は無効となります。
分割協議の結果を書面にまとめたものが遺産分割協議書になります。
この協議書は、後日紛争が生じた際の証拠になるだけでなく、名義変更を行うときの提出書類としても必要となります。
預貯金の解約払戻し
亡くなった人名義の預貯金の解約払戻しは、銀行の窓口に相続届や戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写し、遺産分割協議書などの書類を提出して行います。
相続人が自分で手続きすることも可能ですが、銀行の窓口は平日しか開いていないうえに、予約しないと書類の提出すら受け付けてもらえない場合が大半となります。
行政書士に依頼すれば、戸籍謄本など書類の準備から解約払戻しまで、すべてを代行することが可能です。
自動車の名義変更
自動車の所有者が亡くなったときは、運輸支局で名義変更の手続きが必要となります。(移転登録)
相続によって自動車の保管場所が変わる場合は新たに車庫証明も取得する必要があります。
また運輸支局の管轄が変わる場合は自動車を持ち込んでナンバープレートを交換し、新たに取り付けたナンバープレートに封印をしてもらうことも必要です。
許認可の変更
亡くなった人が仕事として食品営業許可や建設業許可、宅地建物取引業免許などの許認可を受けて事業を行っていた場合は、この許認可についても相続手続きが必要になります。
相続人が事業を引き継がない場合は廃業の届出を行い、事業を承継する場合には相続や変更の届出を行います。
許認可のなかには、相続人が事業を引き継ぐ場合でも、亡くなった人について廃業の届出をしたうえで、あらためて許認可を取り直さなければならないものもあります。
許認可の手続きは行政書士の専門業務ですので、亡くなった人が許認可を受けて事業を行っていた場合には、その事業を引き継ぐか否かにかかわらず行政書士に相談することが重要です。
遺言書の起案や作成補助
遺言書には公証人が作成する公正証書遺言、遺言者本人が自分で作成する自筆証書遺言と大きく2つの種類があります。
代わりに作成することはできませんが、遺言書の案文作成や公証人との打ち合わせのサポートをすることができます。
特に自筆証書遺言は、形式が法律に沿っていなかったり、内容が不明確であると無効になるおそれがあります。
特に自筆証書遺言を作成しようと思う際は、行政書士などの専門家に相談しましょう。
遺言執行
行政書士は遺言書の作成をサポートするだけでなく、遺言執行者になることもできます。
遺言執行者とは遺言の内容を実現する役割を担う人を指し、相続財産の管理や遺言の執行に必要なすべての行為をする権利と義務があります。
相続人や家族、友人などを遺言執行者に指定することもできますが、遺言執行者の責任は大きく、遺言執行のためには一定の知識が必要になります。
適任者がいなければ、法律の知識があり中立的な立場である行政書士などの専門家を検討しましょう。
相続手続きを行政書士に依頼するメリット
相続手続きは相続人が自ら行うこともできますが、行政書士に依頼した場合には以下のメリットがあります。
面倒な相続手続きを幅広く依頼できる
相続手続きは何度も経験するものではなく、手続きも煩雑です。
行政書士であれば、さまざまな相続手続きに対応できます。
手続きが苦手な場合や忙しくてまとまった時間がとれない場合は、相続人の調査から各種の名義変更まですべての手続きをまとめて依頼することも可能です。
手続きのやり直しや漏れを防げる
相続手続きでは、戸籍謄本をはじめ多くの書類を取得する必要があります。
また遺産分割協議書などの作成には法的な知識が必要となり、これらの書類に不足や不備があれば修正や再提出となり、相続手続きに膨大な時間を要します。
また手続きに漏れがあると遺産分割協議をやり直さなければいけない場合もあり、行政書士に依頼して確実に相続手続きを進めることで、無駄な手間を省くことができます。
費用が抑えられる
士業だけでなく信託銀行などの金融機関でも相続手続きの代行サービスを行っています。
金融機関という安心感はありますが、費用は行政書士や司法書士に比べると割高になるケースが多いです。
また相続登記や自動車の名義変更がある場合は、金融機関が紹介する司法書士や行政書士に別途で依頼することになるため、その分の報酬も必要となります。
相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成などは弁護士にも依頼できますが、取扱業務に他の相続人との交渉や紛争解決を含んでいるケースが多く、報酬相場が高く設定されています。
相続トラブルがなく、できるだけ費用を抑えたい場合は行政書士に依頼することが有効です。
行政書士へ依頼したときの費用
行政書士の報酬は自由化されており、一律の報酬は存在しません。
日本行政書士会連合会『令和2年度報酬額統計調査の結果』によると、相続手続きに関する業務の報酬相場は次のとおりです。
→参考出典 日本行政書士連合会『令和2年度報酬額統計調査の結果』
- 遺言書の起案及び作成補助 平均6万8727円 最頻値5万円
- 遺産分割協議書の作成 平均6万8325円 最頻値5万円
- 相続人及び相続財産の調査 平均6万3747円 最頻値5万円
- 遺言執行手続 平均38万4504円 最頻値30万円
あくまで目安となる報酬額です。
相続関係が複雑だったり、取得または作成する書類が多かったりすると、それに応じて報酬額も変わる場合もあります。
正式に依頼する前に見積書を作成してもらうか、事務所ごとに定めている報酬規定を提示してもらうと、報酬額の目安をつけやすくなります。
行政書士への依頼が向いているケース
以下の項目にすべてに当てはまる場合は、まず行政書士に相談することが望ましいです。
- 相続財産に不動産がない
- 相続財産の総額が基礎控除の範囲内で、相続税の申告が不要
- 遺産分割協議がまとまっていて、相続人間の争いがない
これらの項目にあてはまらない場合は、行政書士単独で相続手続きを進めることはできません。
しかしながら、行政書士として他士業と連携している事務所も多くあり、あらゆる相続手続きにワンストップで対応してもらえる可能性があります。
まとめ
今回は行政書士の相続手続きについて解説しました。
相続手続きの専門家と聞いて、弁護士や税理士を思い浮かべますが行政書士も様々な業務に携わることができる専門家です。
中には行政書士にしかできない業務もあり、相続手続きに困った際には手助けすることができます。
相続手続きにおいて、少しでも不安な点や疑問点があれば、早めにご相談ください。
豊富な知識や経験から、状況にあった的確なアドバイスを得ることができます。
↓↓↓個別のご相談はこちら
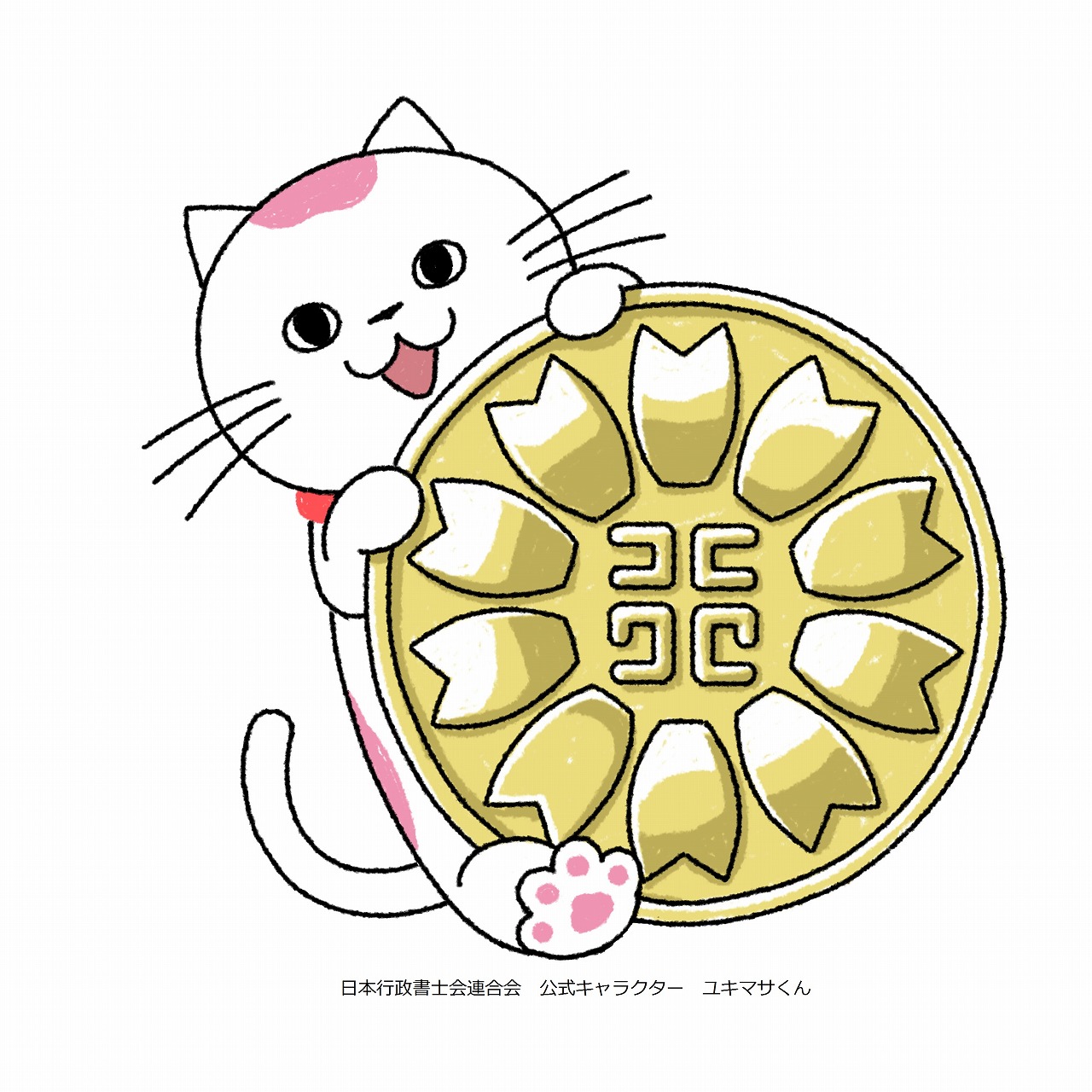


コメント