おはようございます。
東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。
不動産を、相続人同士が共有名義で相続することはケースとしてよくあります。
共有名義にするための理由は様々です。
共有名義は家族間で仲良く公平に相続したようにもみえますが、後々に問題やトラブルが起こる可能性を高く秘めています。
今回は不動産の共有名義について、トラブルや回避方法などを解説します。
少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。
不動産の共有とは
不動産の共有とは、一つの不動産を複数の人が共同で所有することです。
また各共有者が、その不動産を所有する割合を共有持分といいます。
共有持分で登記する場合には、それぞれの共有持分に応じて、共有者 長男が5分の3、共有長女が5分の2というように登記をします。
不動産を共有する場合、各共有者は不動産の一部を使用するのではなく、不動産の全部について使用することができます。(共有物の使用収益権)
しかしながら共有不動産には他の共有者の持分もあるため、1人の共有者だけで好き勝手に使うことはできません。
民法では、共有物に関して、3つの行為の制限を定めています。
▼保存行為
共有物の現状を維持(保存)する行為。
具体的には、建物の修理や不法占拠者への明け渡し要求などがあげられます。
保存行為は、各共有者が単独で行うことができます。
▼管理行為
共有物の性質を変えずに、利用や改良をする行為。
具体的には、賃貸契約の締結や解約、リフォームをして建物の価値を上げることなどがあげられます。
管理行為は、「共有持分の価格の過半数」で決定されます。共有者の多数決ではありません。
▼変更行為
共有物の形もしくは性質に物理的な変更を加える行為や法律的に処分する行為。
具体的には、建物の増改築や建て替え、共有不動産全体の売却などがあげられます。
変更行為には、共有者全員の同意が必要です。
実家を共有する理由
実家などの不動産を相続した場合に、親子・兄弟姉妹が共有で相続するケースがあります。
このケースはどのような場合に共有名義とするか確認します。
分割できない不動産
親の自宅だけが遺産のすべてという場合に、自宅を分割することが物理的にむずかしいために共有で相続するケース。
相続争いで遺産分割がまとまらない
遺産分割協議において相続争いになり話し合いがまとまらないと、いつまで経っても遺産が相続できません。
法的には相続が発生してから遺産分割協議が成立して相続登記が行われるまでは、相続財産は各相続人が法定相続分で所有するとされるため、共有の状態が続きます。
とりあえず共有
親子や兄弟姉妹の仲が良く、あまり深く考えずとりあえず共有名義にしておくケース。
不動産共有によるトラブル
共有不動産は各共有者が自由にできないという制約があります。
そのために、さまざまな場面でトラブルになりがちです。
売りたくても売れない・貸したくても貸せない
実家の空き家を売却したくても、共有者のうち1人でも反対するとできません。
たとえば兄は経済的に困っているので、少しでも早く実家の空き家を売却してお金に換えたいと思っていても、経済的にも成功し裕福な弟が売却に反対した場合は、売ることができません。
また売却自体には共有者全員が同意していても、売却金額や売却時期について意見がまとまらずになかなか売れないケースもよく見られます。
実家の空き家を賃貸にすることは、売却以上に難しいといえます。
たとえば、兄弟姉妹の1人が、空き家を貸家にしたいと提案しても、他の兄弟姉妹が賃貸経営に対して不安やわずらわしさを感じていたり、そもそも実家に他人を住まわせたくないと考えていたりする場合に反対することも少なくありません。
空き家を賃貸することは共有物の管理にあたるため、共有持分の価格の過半数に届く人数の合意があれば可能ですが、反対意見を押し切って強引に進めてしまうと、兄弟姉妹の間にわだかまりが生じ、のちのちに遺恨を残す可能性もあるため、十分な注意や配慮が必要です。
売却や賃貸を巡って兄弟姉妹間のトラブルになる場合、以下のような要因が考えられます。
実家に対する想いがそれぞれ異なる。
兄弟姉妹間に経済的な格差がある。
不動産に対する基本的な考えが異なる。
また相続時には兄弟姉妹の意見が一致していても、時間の経過と共に考えが変わることもあります。
管理の負担が片寄る
空き家の管理もトラブルになる原因の一つです。
空き家の管理には、除草・剪定、ごみの片づけ、掃除など、多くの手間ひまがかかります。
共有とはいっても、現実には近くに住んでいる兄弟姉妹など一部の共有者に管理の負担がかかることが多く、不公平感は否めません。
また毎年の固定資産税納税通知書は、共有者のうちの1人に送られてきます。
なかには納税通知を受け取った人が税金全額を支払い、他の人は負担をしない場合もあり、負担している人の不満も生じます。
仲たがいや代替わりがあるとさらに困難
兄弟姉妹の仲が良ければ問題も表面化しません。
しかし何かをきっかけにお互いの関係が悪化すると、たまっていた不満も表面化し、共有不動産の保存・管理・変更行為がむずかしくなります。
また共有者のうちの誰かが亡くなり代が替わっていくと、だんだんと血縁や日常の付き合いも薄くなるため、お互いに気持ちも通じ合わなくなり空き家の売却や活用についても話がまとまりづらくなっていきます。
少なくとも近しい兄弟姉妹が元気なうちに共有状態を解消しておくことが重要です。
親子の共有なら大丈夫?
亡くなった父の自宅を母と長男の共有名義にするなどのケースもありますが、親子の共有であれば、トラブルにはならないのでしょうか。
兄弟姉妹間での共有よりはトラブルは少ないとは言え、母と長男の考え方が違っていれば、やはりトラブルになる可能性はあります。
また母が亡くなったときに、母の共有持分を他の兄弟姉妹が相続すると、その時点から兄弟姉妹の共有になってしまいます。
これを避けるためには、母の共有持分は長男が相続し、兄弟姉妹は他の財産を相続するなどの対処法を話し合っておくことが大切です。
トラブルの解決策
共有名義の状態であれば、いずれトラブルが起こりえます。
トラブルを避けるためには、早めに共有の状態を解消しておくことが重要です。
共有不動産を単独所有にすることを「共有物の分割」といいます。
共有物の分割にはいくつかの方法があります。
▼現物分割
共有持分に応じて、物理的にそのまま分ける方法です。ただし、狭い土地や分割後の各土地の条件に著しく差が生じる場合には話がまとまらないおそれがあります。
▼代償分割(価格賠償)
共有者のうちの1人が、他の共有者から持分を取得し、その対価を支払う方法です。
▼換価分割
共有不動産を第三者に売却し、売却代金を分ける方法です。
各共有者は他の共有者に対して、いつでも分割の請求をすることができます。
話し合いで共有が解消できることが望ましいですが、話し合いがまとまらない場合は、共有物分割訴訟によって裁判所が分割方法を判断することもあります。
なお共有者のうちの一部の人が共有状態から抜けたいときは、その持分を放棄する方法と、持分を第三者に売却する方法があります。
共有者が持分を放棄した場合には、他の共有者がその持分を取得することになります。
共有持分を第三者に売却した場合、他の共有者と第三者との間にトラブルが生じる可能性もあるため、一般的には避けたいところです。
まとめ
今回は不動産を共有名義で相続することについて解説しました。
さまざまなトラブルを引き起こす可能性があるため、共有で相続することは極力避けるべきです。
相続前であれば、実家の相続についてあらかじめ家族で話し合うべきです。
すでに兄弟姉妹が共有で相続している場合には、できるだけ早く共有状態を解消することを検討しましょう。
分割方法についてはいろいろと検討しなければならないことが多々あります。
不明な点や気になる点があれば、法律専門家に相談することも重要です。
豊富な知識から的確なアドバイスを得ることが可能です。
↓↓↓個別のご相談はこちら
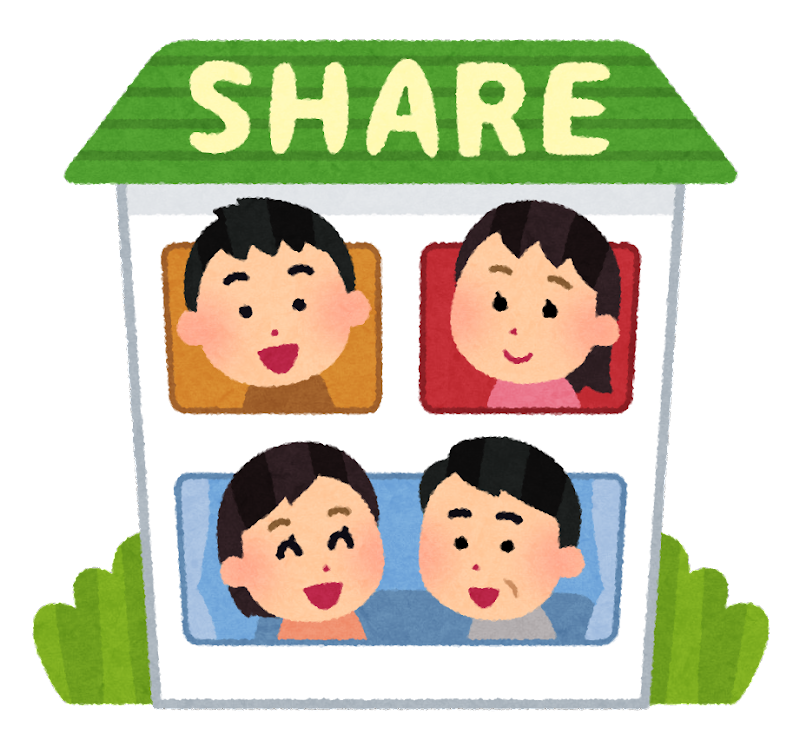


コメント