おはようございます。
東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。
亡くなった人(被相続人)の死亡退職金は、企業の退職給与規定等でその遺族が受取人として指定されていることが一般的です(遺族の中での受取人の順位が定められていることもあります)。
この死亡退職金は被相続人の相続財産になるのか!?それとも受取人固有の財産になるのか!?
さらに死亡退職金に相続税はかかるのか!?
今回は死亡退職金について、注意点なども含め解説していきます。
少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。
死亡退職金とは
在職中に亡くなられた時に、本人に代わって遺族が受け取ることができるお金を死亡退職金といいます。
退職金制度は勤務先が任意で採用する制度であるため、就業規則や退職金の規定を確認し死亡退職金を含む退職金を受け取れるかどうかを確認しておきましょう。
死亡退職金は、「死亡退職手当」や「死亡退職慰労金」といった名前で支給されることもありますが、弔慰金とは異なりますので注意しましょう。
死亡退職金が勤務先の規定で定められている場合は、一般的に勤務先から死亡退職届に必要書類を添えて勤務先に提出することになります。
<死亡退職金を受け取る際に必要な主な書類>
- 死亡退職届・退職金請求書
- 亡くなられたことがわかる書類(死亡診断書や除籍謄本など)
- 亡くなられた従業員と請求者との関係がわかる書類
- 戸籍謄本など
死亡退職金は受け取った人の財産か?相続財産か?
亡くなった人(被相続人)が勤務していた会社の退職給与規程において、受取人の指定がされている場合には、死亡退職金は受取人固有の財産となります。
「受取人固有の財産」ということは、相続財産には含まれません。
遺産分割を経ることなく受取人とされた遺族は、死亡退職金を受け取ることが可能です。
一方で退職給与規程において受取人の指定がされていない場合には、相続人の共有の相続財産となります。
死亡退職金は遺産分割の対象となる相続財産に含まれます。
遺言がある場合はそれに従い、遺言がない場合は遺産分割協議において全員の合意のもとで死亡退職金の受取人を決める必要があります。
死亡退職金に相続税がかかるか?
死亡退職金は「みなし相続財産」となり、原則として相続税の対象となります。
みなし相続財産とは、亡くなった人が生前から持っていた財産ではなく、亡くなったことがきっかけで受け取る財産のことです。
死亡退職金や生命保険の死亡保険金などが該当します。
これらの財産については亡くなられた方から引き継いだものではありませんが、「実質的に相続で得た財産である」とみなされ、原則相続税の課税対象となります。
なお課税対象となる死亡退職金には条件が定められており、亡くなられた方の死亡後3年以内に支給額が確定したものが、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
一方で死亡後3年を経過した後に支給額が確定したものは相続税の対象になりません。
この場合は、受取人の所得税の課税対象となります。
支払額の確定した時期に注意しましょう。
死亡退職金には非課税枠があります。
死亡退職金の金額が「500万円×法定相続人の数」の範囲内であれば、相続税はかかりません。
死亡退職金の注意点
弔慰金の扱い
従業員が亡くなると、勤務先から死亡退職金とあわせて弔慰金や花輪代、葬祭料などが支給されることがあります。
これらは基本的に非課税です。
しかし大きな金額になると、実質は死亡退職金等に該当すると認められ、相続税の対象となる場合があります。
死亡退職金の受取人を遺言で指定できる!?
亡くなった人(被相続人)の勤務先企業の退職給与規定等に死亡退職金の受取人が定められている場合、死亡退職金はその受取人固有の財産となります。
亡くなった人(被相続人)が生前にその受取人と異なる人を遺言で受取人として指定することはできないと考えられます。
死亡退職金をきてされている人以外が受け取る場合
死亡退職金を指定されている人以外が受け取る場合
退職給与規定等に死亡退職金の受取人の第一順位者として配偶者が定められているケースが大半です。
たとえば配偶者と長男で話し合って死亡退職金は長男が取得するとした場合に、死亡退職金は配偶者の固有の財産となり遺産分割の対象とならず、まず配偶者へ相続税の課税対象となり、長男は配偶者から死亡退職金相当を贈与により取得したとして贈与税が課税されます。
具体的には、業務上の死亡の場合は給与の3年分、業務外の死亡の場合は給与の半年分が弔慰金と認められる範囲の目安となります。
まとめ
今回は死亡退職金の扱いについて解説してきました。
死亡退職金は、退職給与規程によって受取人が指定されているかによって、相続における扱いが異なってきます。
まずは退職給与規定がどのようになっているか確認をしておくべきでしょう。
不明な点や疑問点があれば法律専門家へ相談することが最適です。
豊富な知識から的確なアドバイスを得ることができます。
↓↓↓個別のご相談はこちら
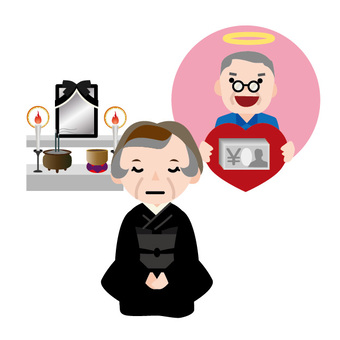


コメント